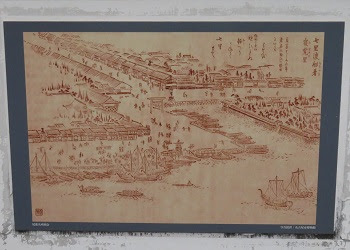3日目は昨日の終着点の笠寺観音から豊明に向けて出発します。笠寺観音は尾張四観音のひとつに数えられます。本堂は宝暦13年(1763)に建てられた建物です。聖武天皇の時代に呼続浦に漂着した霊木を禅光上人が彫ったと伝わる十一面観音が本尊です。多宝塔の前には人質交換の碑があります。これは幼少時代の徳川家康(竹千代)と織田信長の兄の織田信広がこの笠寺観音で人質交換されたことに因んで建てられた碑です。笠寺観音を出て少し歩くと笠寺一里塚があり、大きな榎が立っています。この榎は一度枯れかけましたが、平成6年春、市が幹に空いた穴をふさぐ手術をして蘇ったそうです。
笠寺観音本堂笠寺の一里塚の榎